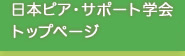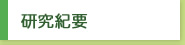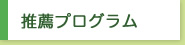�����I�v
�����I�v�ɂ���
�{�ψ���ł́A�����I�v�u�s�A�E�T�|�[�g�����v�̕ҏW�E���s�Ɩ����s���Ă��܂��B�s�A�E�T�|�[�g�͌��݁A���{�̊w�Z����ɐZ�����͂��߂Ă��܂��B�s�A�E�T�|�[�g�̎��H���L���s���Ă���Ƃ������Ƃ́A����̗��_���⌤���ɑ����ɖ𗧂��ƂƎv���܂��B�����ŁA���K�v�Ȃ̂͊F����̎��H�̕ł��B�ǂ̂悤�Ɏ��{���A�ǂ̂悤�Ȍ��ʂ�����A�ǂ�Ȗ�肪�����A�ǂ������������Ƃ������Ƃł��B���̏������̏�Ƃ��Č����I�v��傢�ɗ��p���ĉ������B
��������}���ْ������s���̂h�r�r�m�ԍ����擾���܂����B
����}���قɐ\�����Ă��������I�v�u�s�A�E�T�|�[�g�����v���A2007�N5��29���ɁA�������s���̂h�r�r�m�ԍ����擾���܂����B�擾�ԍ��́A�h�r�r�m1882-0808�ł��B����݂Ȃ���̗͂ŁA����ɏ[�����������I�v�Ɉ�Ă܂��傤�B
���I�v���s�܂ł̗���i�\��j��
| 2��28�� | ���e���� |
| 3�� | �ꎟ�R���i�y�[�W���E�̍فE���e���i�̗L�����̊m�F�j ��̏ؔ��s ���ǎ҂̊���U�� |
| 4�� | ���ǎ҂ւ̈˗� |
| 5������ | ���nj��ʂ̏W�� |
| 6�� | ���e�҂ɍ��nj��ʂ̒ʒm �i��ɑ����ĐR���ψ���������B�K�v�ɉ����ĐR�c�j |
| 7�� | �ē��e��t���� |
| 7���`8�� | �f�ژ_���̌��� �i��ɑ����ĐR���ψ���������B�K�v�ɉ����ĐR�c�j �p���A�u�X�g���N�g�쐬�̈˗��i���ی𗬈ψ���j |
| 9�� | �����ЂɈ˗� ���e�̃`�F�b�N ���e�̃`�F�b�N |
| 12�� | ���� |
�������\�_���W�̎��M�ɂ���
�@���\�҂͈ȉ��̇@�`�B��K�����m�F�̏�A�����g�̔��\�ɏ����ĕK�v�ȃe���v���[�g���_�E�����[�h���āA�����܂łɎ��M�E��o���Ă��������B
�A���\�_���W���e�K���E���M�v�j
�C���\�_���W�e���v���[�g�i�����E���H���\�p�j
�D���\�_���W�e���v���[�g�i����V���|�W�E���p�j
�E���\�Ɋւ���@�ދy�є��\�������ɂ��āi���n����̂��m�点�j
���|�X�^�[���\�́A�\�����̔��\�ҁE���\�e�[�}�E�T�v�����f�ڂ����Ă��������܂��B
��o����7��31���i�j���ߖ�
�y�������y�[�W�ɖ߂�z
���₢���킹�E���e�̒�o��
��739-0046�@���L���s���R1-1-1
�L����w��w�@�l�ԎЉ�Ȋw�����ȕ���������H�����Z���^�[��
���{�s�A�T�|�[�g�w����I�v����
���ߔN�x�̌����I�v�ɂ��Ă͍�������}���قɔ[�{���Ă���܂��B�ߔN�x�̏o�ŕ��̑����͍�������}���قɔ[�{���Ă���܂��B�����p�̕�����������}���كT�[�`�iNDL�T�[�`�j���猟���̏�A�����p���������B